



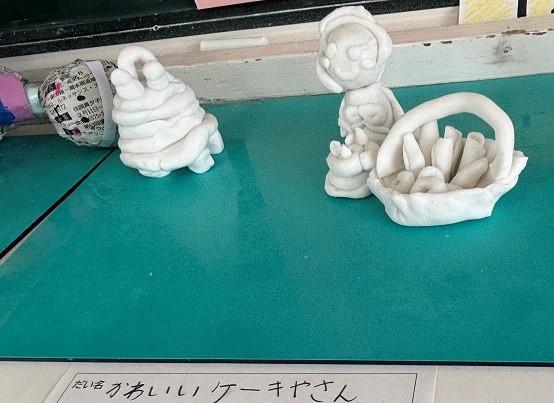
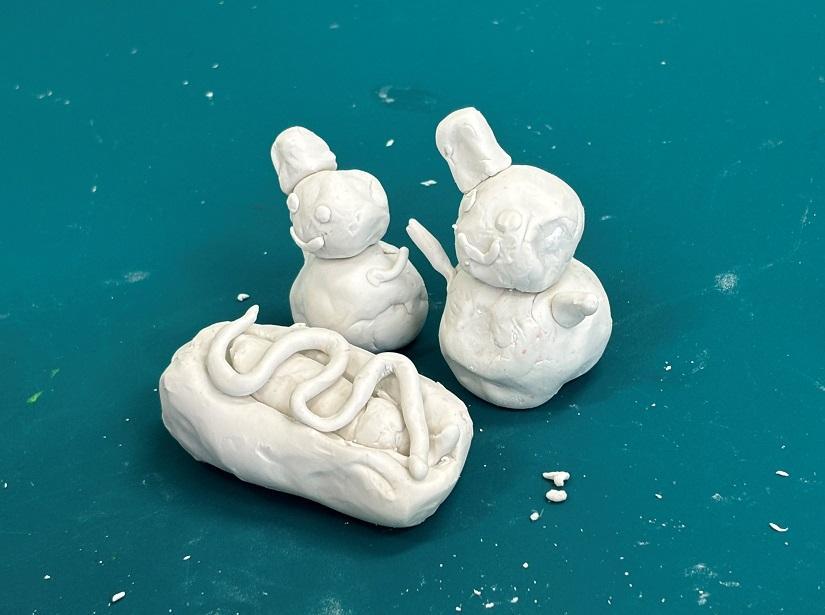
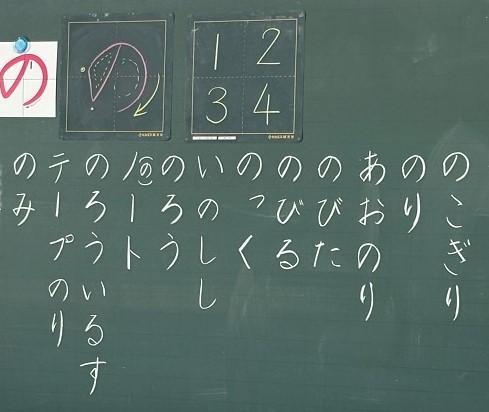

学校の先生を30年以上してきましたが、子どもは「ウソ、ごまかし」をしてしまうことが多々あります。時代が変わっても、勤め先の学校が変わっても「ウソ、ごまかし」が0だったということはありません。
大人であっても、「ウソ、ごまかし」をしてしまうことがあると思います。
一方で、思いやりの「ウソ、ごまかし」もあります。他人に真実を伝えない方がいい場合に、使うこともあるのではないでしょうか。
児童集会で、子どもたちに話したことをご紹介します。これは悪い意味での「ウソ、ごまかし」についてです。
「ウソ、ごまかし」はよくありません。
自分が何か悪いことをしたときに、それを尋ねられたら「いや、知らないよ」とか「自分はしていない」「(自分はさぼったのに)もうやったよ」あるいは「それは叩(たた)いたんじゃなくて、たまたま当たっただけだよ」ということがありますね。また、そう言っている友達を見たことがあると思います。
悪いことをした時にウソをついたり、ごまかしたりするのはいけないことだとみんな知っているのに、どうしてするのでしょうか。
それは、人間や動物には自分にとって危険なことや嫌なことから逃げようとする本能があるからです。
悪いことがわかってしまうと、叱られますよね。それは嫌ですから逃げるために「ウソやごまかし」をしてしまうのです。
話を聞いている先生や大人は、子どもがウソを言っていたり、ごまかしていたりしていると思うこともあります。だからと言って全部「ウソやごまかし」だと決めつけてしまわないようにしています。それと、子どもの言っていることを信じてあげたい、という気持ちも働きます。
なので、「ウソやごまかし」が通ってしまうこともあるのです。
するとどうなるでしょう。
「ウソをついて叱られずに済んだ。また次もウソをついて叱られないようにしよう」という気持ちが働きますよね。その子はウソを繰り返すようになります。何回もウソをついていると、周りの子にウソつきだと思われます。やがて自分では気づかないうちに、大切な信用を失ってしまいます。
(続きます)