
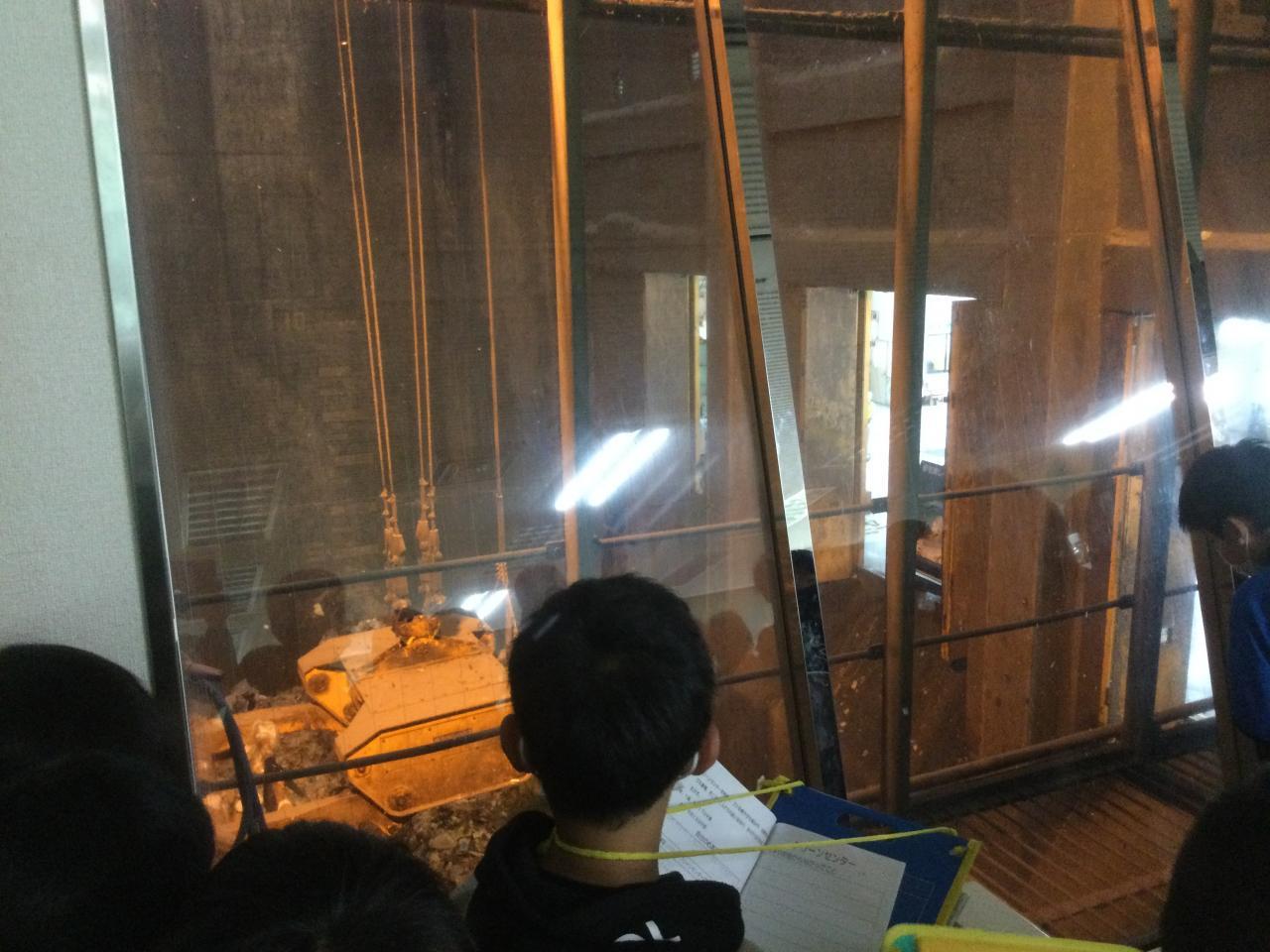


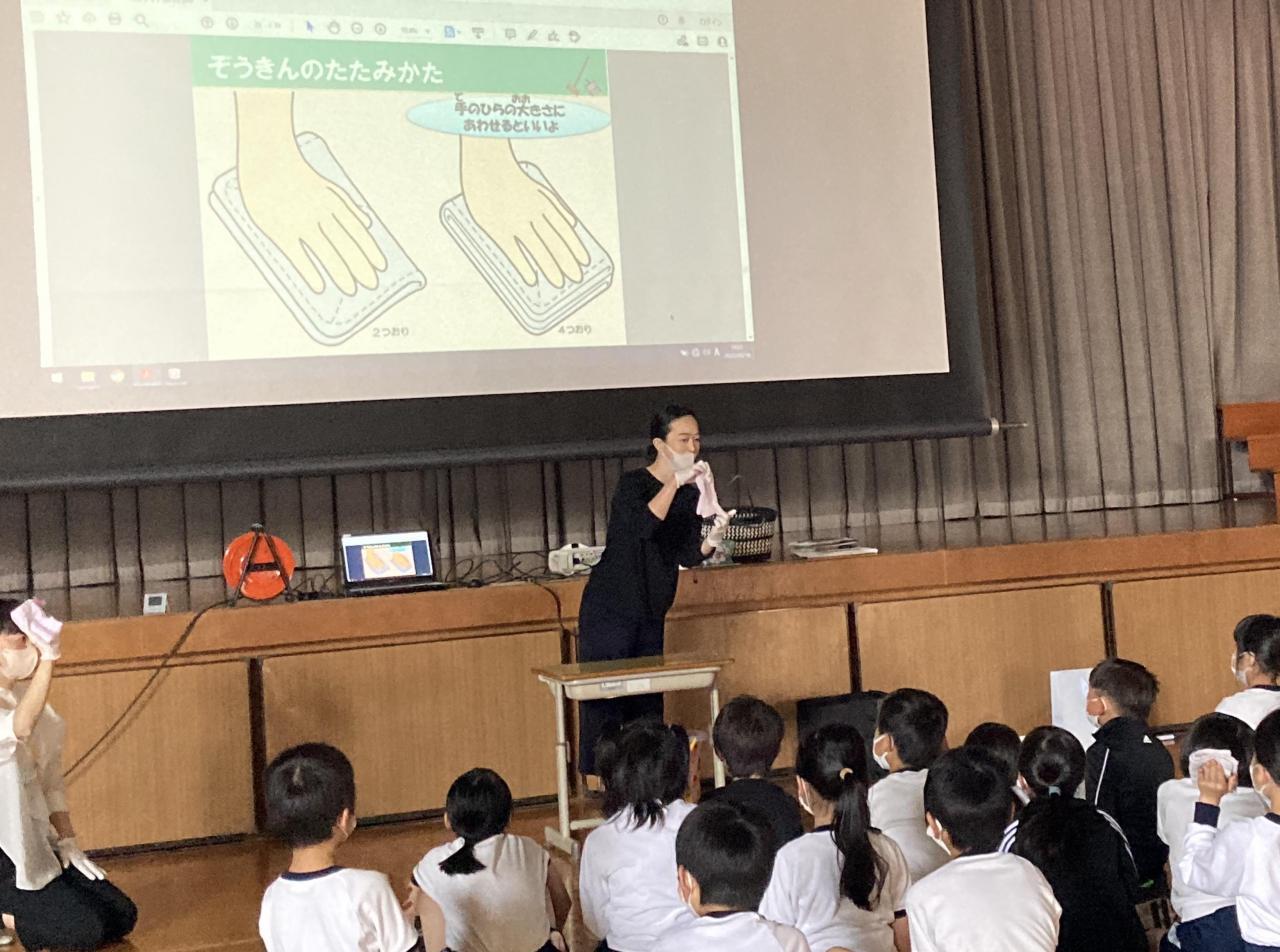





いつも読んでくださり、ありがとうございます。今回も長くなってしまいますが、どうぞよろしくお願いします。保護者の皆様におかれましては、引き渡し訓練(6/1)がスムーズになるようご協力くださり、ありがとうございました。
校区の方から次のようなお言葉をいただきました。
「5年生と2年生ぐらいの女の子が登校している途中、2年生?の子がこけて、両膝をすりむいていた。5年生?の子が自分の持っていた絆創膏で手当てをしていた。とてもうれしい気持ちになりました。」
おまわりさんにしっかりあいさつができたり、止まってくださった車に頭を下げて通ったりなど私が目にする以外にも、地域の方がうれしくなるような行動をしているのだなあと感心しています。
一方、こんな出来事がありました。
歩道から車道側へはみ出ながら登校してくる男の子を見かけました。私は、その子が近づいてきた時に立ち止まらせて、注意をしました。
「車が通る道へはみ出たら、あぶないよ。」
自動車と接触しかけたということではなかったので、慌てず諭すように注意をしたつもりでした。
男児は私と目をあわさない聞き方をしていました。私の立場からすると目を合わせてくれないので、注意の内容が伝わっているのかなと不安になりました。
周りに友だちがいましたから、気まずかったのでしょうか。それとも、自分は注意されるようなことをしているつもりがないのに、怒られていると思ったのか真意は分かりません。が、ふてくされているという態度ではありませんでした。
あれこれ考えてみたのですが、注意を受けたことに対する戸惑いという表現が一番当てはまると思いました。今は以前に比べ、親御さん以外に大人が子どもを叱る場面はずいぶん減ったのではないでしょうか。
保護者の方も叱り方は様々だと思いますので、子どもがとらえている叱られる基準に格差が出てきたと感じています。
(続きます)