



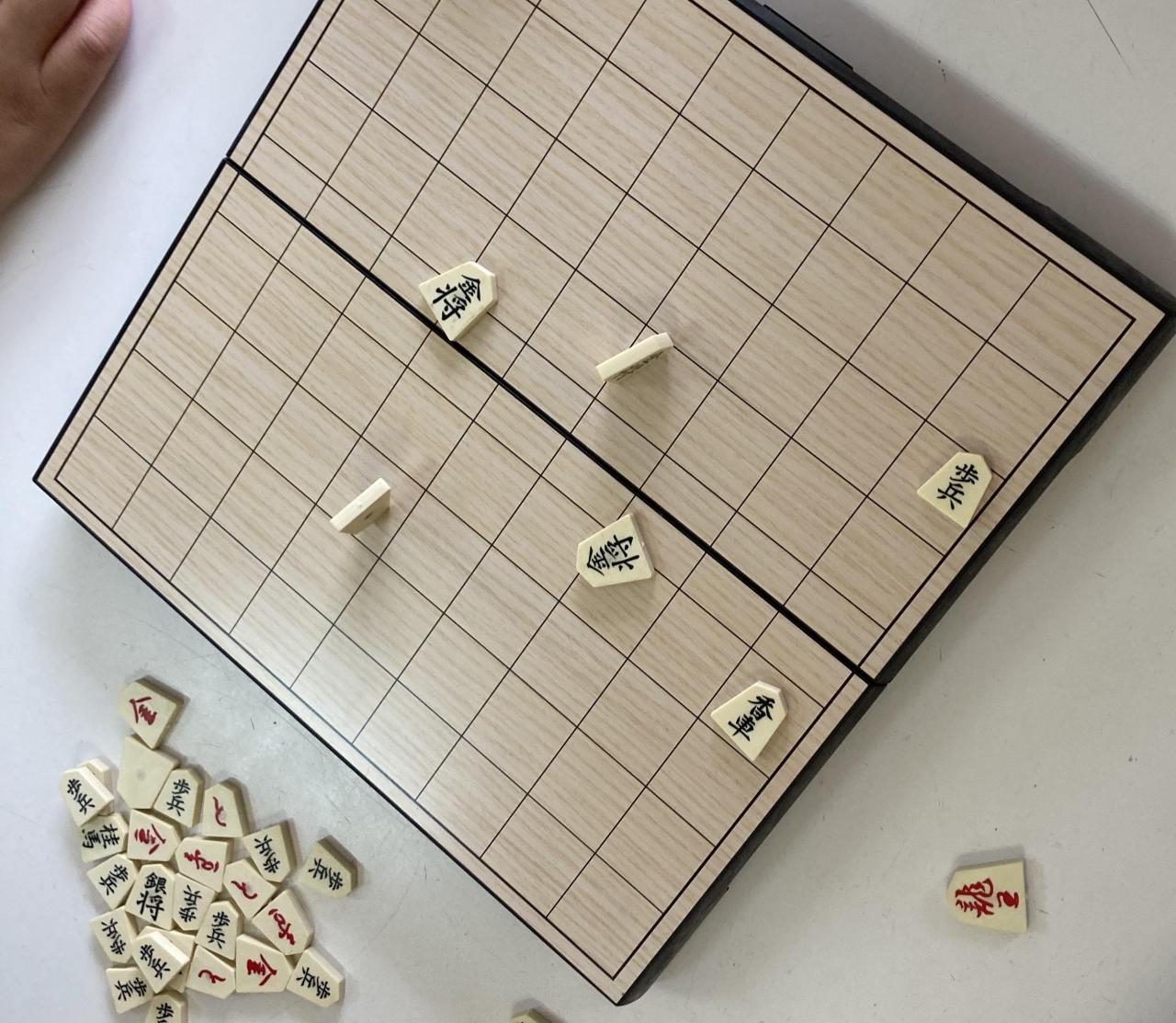

(続きです)
次は叱るほうの立場で考えます。
まず、絶対にしてはいけない叱り方は「いきなり怒鳴る」です。
例えば、「(大きな声で)何やってんの!」「弟がいやがってるでしょ」です。他には「(大きな声で)こらー(怒)いいかげんにしろ」「ゲームしてないで、早く宿題しろ」です。
このような叱り方を繰り返された子どもは、オドオドした性格かまたはピリピリした性格になるそうです。理由は、次の通りです。
いきなり怒鳴られると、子供は自分の行為が叱られる事であると認識していない状態で、突然強いショックを受けることになります。それが繰り返されると、いつ強いショックを受けるのか常に心配していなくてはなりません。
心が安定せず過ごしているので内向的な子であれば、オドオドした性格、外向的な子であればピリピリした性格が形成されます。
そして、いつ怒鳴られるかわからないので、親を避けるようになります。その後も無意識に避けるようになり、心を閉ざしていくでしょう。
子どもの様子がおかしい時に「何かあったの?」と優しく聞いたつもりでも「べつに」と返されてしまいます。
「いきなり怒鳴る」は経験ある方がいらっしゃるのではないでしょうか。もちろん私もあります。
改善の方法としては、最初に怒鳴らないことです。先例を改善すると「弟が嫌がっているからやめなさい」「やめなければ大きな声で叱るよ」としてみてください。
ゲームについてもしっかり話し合っておいてルールを決めておけば、「ゲームの約束あるよね」「それを守れなかったら本気で叱るよ」と予告しておくのがいいでしょう。
つまり子ども自身の行為が、叱られるに値することだと理解させることが重要なのです。
大きな声を突然出していいのは、危機回避の時です。例えばボールを追っかけて車道に飛び出そうとしている子どもは止めなくてはなりません。一瞬でも待てないときは大きな声を出します。
叱る時はいきなり怒鳴らず、心の準備をさせることで、ダメな理由を子どもに理解させることができるのではないでしょうか。
そして、「あなたが同じ間違いを繰り返さない正しい人になってほしい」というメッセージを伝えることができると思います。
今、地域の方に叱られることがほとんどなくなった子どもたちは、家と学校で価値観を形成していきます。ご家族の皆様と、学校がより協力して子どもたちを育て、将来の社会生活につなげてまいりたいと思います。
また、子どもが間違ったことをしているときに、地域の方に叱ってもらえるようなつながりを深めることも必要でしょう。どうぞよろしくお願いいたします。
初めに話題にした男児は以降、車道にはみ出ないように登校しています。しっかり分かってくれていました。これからも気を付けて登下校してください。
最後まで、読んでくださりありがとうございました。