





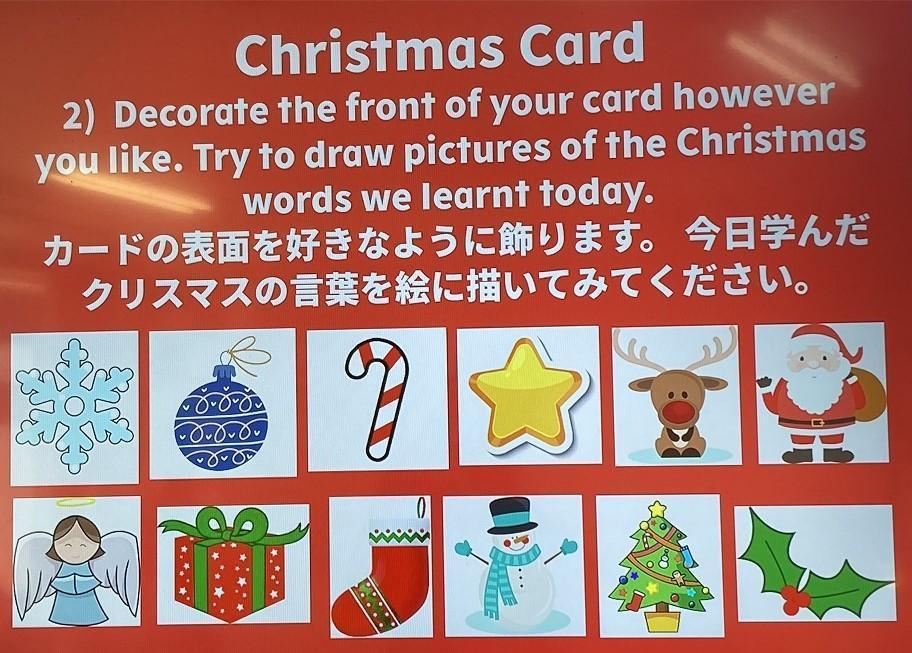

(続きです)
③新しい発見
道徳の時間に新しい発見(気づき)を得るために必要なこと、それは
「教材のたった一つの場面について、児童生徒全員が自分の考えを言う、そしてその考えをまわりの友だちが受け入れる」です。
私が授業で試したところ、子どもたちの感触が最も良かった方法でした。と言いますのも、それまでは、道徳の指導書と私が経験したことをまとめ、子どもに語る授業をしていました。多少子どもが発表したとしても、最後は私がまとめてしまうから、子どもにとっては、おもしろく(新しい発見が)なかったのだと思います。
しかし、先生の考えやよく手が挙がる子の発表だけよりも、クラス全員が発表すると、本当に多様な考えが集まります。子どもたちは、「あの子はどんな発言をするのだろう」とわくわくした気持ちで聞いていました。実は私が、「あっ! そういう考え方ができるんだ」と驚かされることも多かったのです。
④道徳的実践力を養うために
もうひとつ良かったのが、「自分の考えが変だったら恥ずかしい」と思っていた子が、別の子の同様な意見に安心し、自らの考えに自信を持つことができたことです。また、多様な意見が交わされる授業が積み重なると、子どもたち全員の道徳的思考がだんだん深まっていきます。
私にとっては、全員が考えを言う(教師の意見は、なしです)方法に変えてから、道徳の時間でなくても、子どもたちが自律して学校生活を送るように変化したと言えます。
私の尊敬する先生が次のように書いていました。
「実生活で出合う道徳的問題では、多様な考えに耳を傾けながら最後は自分で決断を下さなければならない問題があります。考え、議論しながら最後は自分自身に向き合う。それが道徳で育てたい自律です。」
今回は、道徳について書かせていただきました。ねらいとするテーマ(思いやり、規則の尊重、生命の尊重、・・・)はありますが、そこにたどり着くことが目標ではありません。
一つのテーマを題材として自分の生き方を考え、自律して他者と共によりよく生きていくことが目標になるのだと思います。
道徳の授業は引退(?)している私ですが、子どもたちとの触れ合いの中で、今後道徳性のあるコミュニケーションを数多くできるといいなと思っています。
今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。