







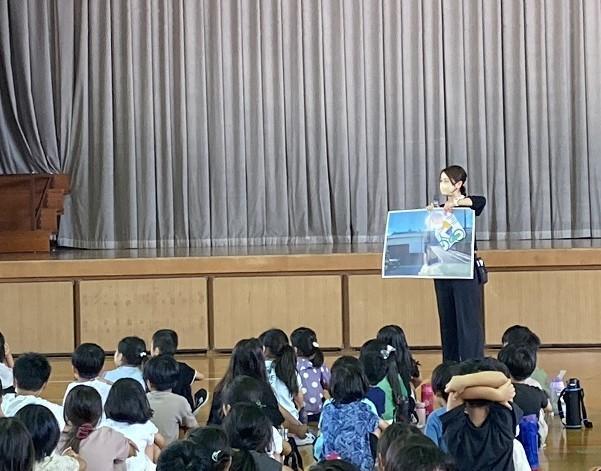
Aさんという子どもが「○○さんに嫌なことを言われた」「△△君に物を投げられた」「□□ちゃんが、おもちゃをひとり占めして貸してくれない」・・・・などと、訴えてきたとします。子ども同士で解決できることが理想ですが、Aさんが対処できなければ、放置できません。
そこで先生や親として、対象になっている○○さん、△△君、□□ちゃんの人となりを想像します。
彼ら(○○さん、△△君、□□ちゃん)が、普段そのような悪い行為をしない子であれば、行為に至った状況を確かめると思います。ひょっとしたらAさんにその行為を招く原因があったのではないか、とも考えます。
しかし彼らが普段から同様の行為が多い子であれば、おそらく「悪いのは○○さん(△△君、□□ちゃん)だ」と心の中で決めつけてしまうのではないでしょうか。
つい、その言葉を口に出してしまうことがあるかもしれません。
このことについては、経験ある方も多いと思います。
しかし、口に出すことも、心の中で決めつけてしまうこともよくないと私は思います。正直言いますと、私は口に出したり、心の中で決めつけたりしてたくさんの失敗をしてきました。
たとえ〇〇さん(△△君、□□ちゃん)が最初からトラブルを起こしていたとしても、決めつければ失敗します。
なぜ、失敗するのでしょうか。
「悪いのは○○さんだ」と言ってしまう失敗について
先ほどの例で言うとAさんが訴えてきたときに、Aさんの正当性を認めてAさんに安心感を与えようとする気持ちが働きます。確かに○○さんは普段から良くない行為が多いので仕方ないかもしれません。
しかし「悪いのは○○さんだ」と言ってしまうと、その時の状況把握や原因追究が疎(おろそ)かになります。
また、「悪いのは○○さんだ」という言葉は、○○さんにいずれ聞こえていくことになります。その言葉を聞いた○○さんの心情はどうでしょうか。
伝え聞いた話は、自分への誉め言葉なら喜びが倍増します。反対に自分にとって嫌な話は、悲しみや怒りが倍増してしまいます。
ネガティブな気持ちが先行すると、○○さんは自分の悪い行為を素直に反省できないのではないでしょうか。また、言葉を発した人は○○さんとの信頼関係を作れなくなってしまいます。
そこで、Aさんに対して安心感を与えかつ、その後冷静に対処するために、次の様に言うのはいかがでしょうか。
「Aさんはつらい思いをしたね、○○さんにも聞くから、これから同じことがないようにしていくね。」
(続きます)