220622 朝の読み聞かせ 開始

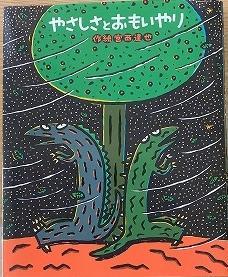

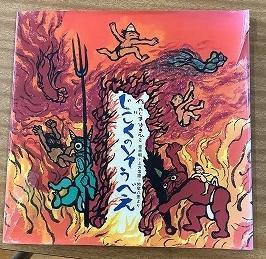

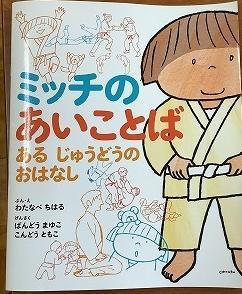
南あわじ市では、学習の基盤となる資質能力である言語能力の育成に向けて、読書活動の充実、習慣づくりを行い「読解力」の向上を目指しています。「絵本の読み聞かせ」もその取組の一つとして市内小中20校で学校の実情に合わせて取組を進めています。本校でも、先日、「一冊の本が子どもを変える~こんなときには、こんな絵本を~(黎明書房)」の著者、教育アドバイザーの多賀一郎先生を講師として小中学生に「読み聞かせ」をしていただき、その後、教職員は研修会を実施しました。「中学生に読み聞かせ??絵本??」という思いもあったのですが、「とにかく、始めてみよう」と本日スタートしました。「??」スタートでしたが、生徒たちが「読み聞かせ」を受けている様子を見ると、しっかりと聴き、受け止めていました。
話は変わりますが、私は、数学教師です。数学が分からなった生徒はよく「数学なんて何のやくに?つかわへんやん」といいます。確かに、数学は数学的考え方を通して「論理的思考」「解析力」・・・等の育成が期待されますが、じゃ直接、教科書の内容で「飯を食べていく」人はほんのわずかです(上記の資質能力を伸ばして職とする人は多くいます)。「じゃなんで数学をやるの?」となりますが、人が本来持つ知的好奇心のおもむくままに考えることで「楽しく頭の体操」をすることに他なりません。「頭の体操なら別に数学じゃなくても」ということになりますが・・・今は就職、進学に向けてどうしても、嫌でも教科書数学が必要になります。「じゃ、数学の教科書て゛面白く頭の体操をしようよ」と日々、数学教師は授業を考えています。
閑話休題。すぐに「中学生に絵本??読み聞かせ?効果あるの?」なんて考えてしまいますが、専門の数学でも「直接的に効果」を狙っている訳ではないことを考えると、「楽しそうだし、とにかくやってみよう」というスタートもいいのかなとしっかり「読み聞かせ」を聴いている生徒を見て改めて思いました。朝読書の回数が1回減りますが、読書は習慣さえついてしまえば、「読む時間の保障」なんて改めてしなくても、休み時間やおうちでのスキマの時間に自然と本に手を伸びますよね。
学術的な読み聞かせ効果については下記のアドレスで研究報告されています。ぜひ、「読み聞かせ?そんなの必要か?」と思われる方は参考までにご覧ください。本校では、8月に報告書を書かれてた鳴門教育大学森慶子先生を講師に迎え、研修会を行います。
中学生に対する絵本の読み聞かせの効果の研究
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jtsjs/134/0/134_83/_pdf