


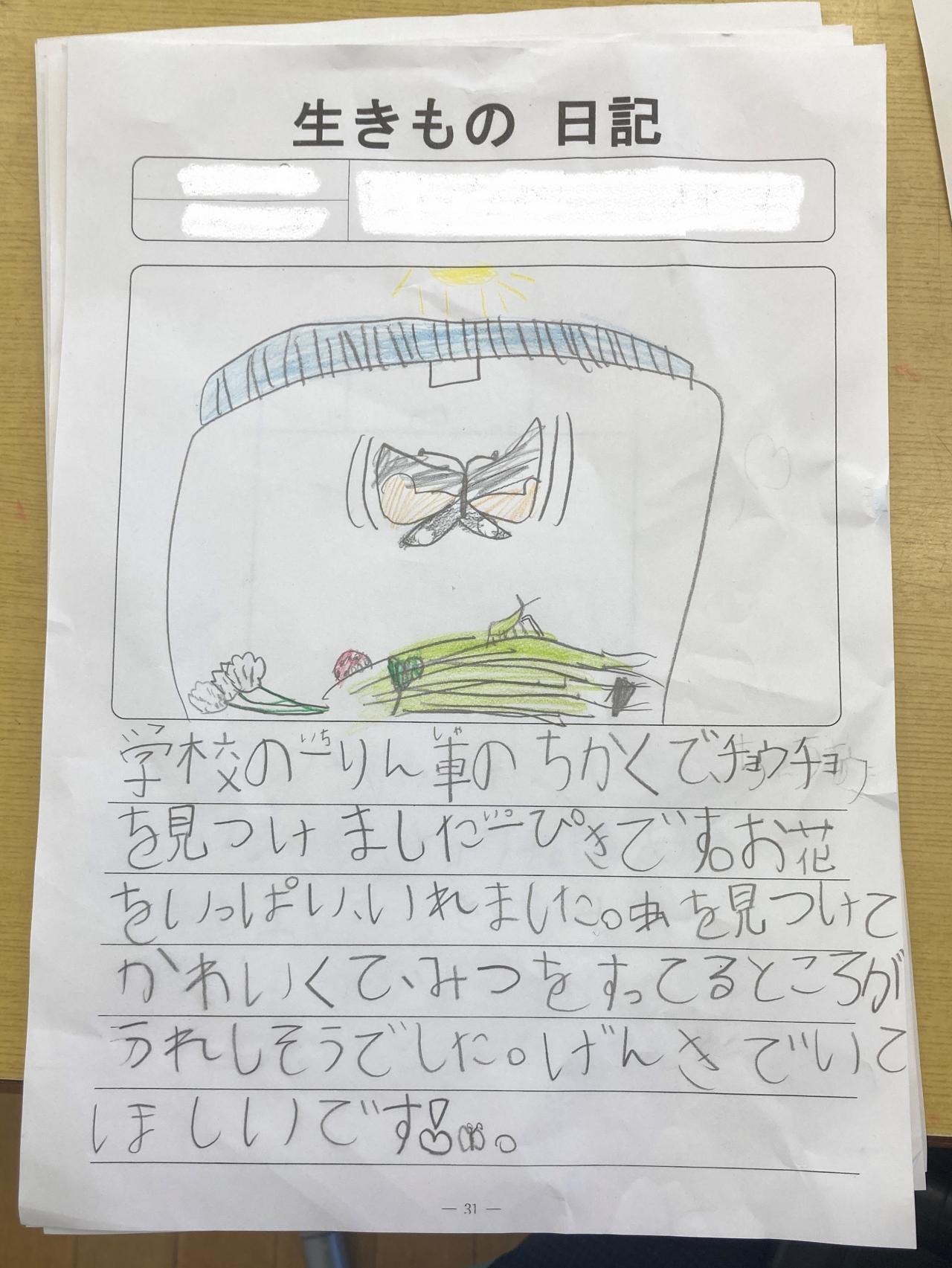

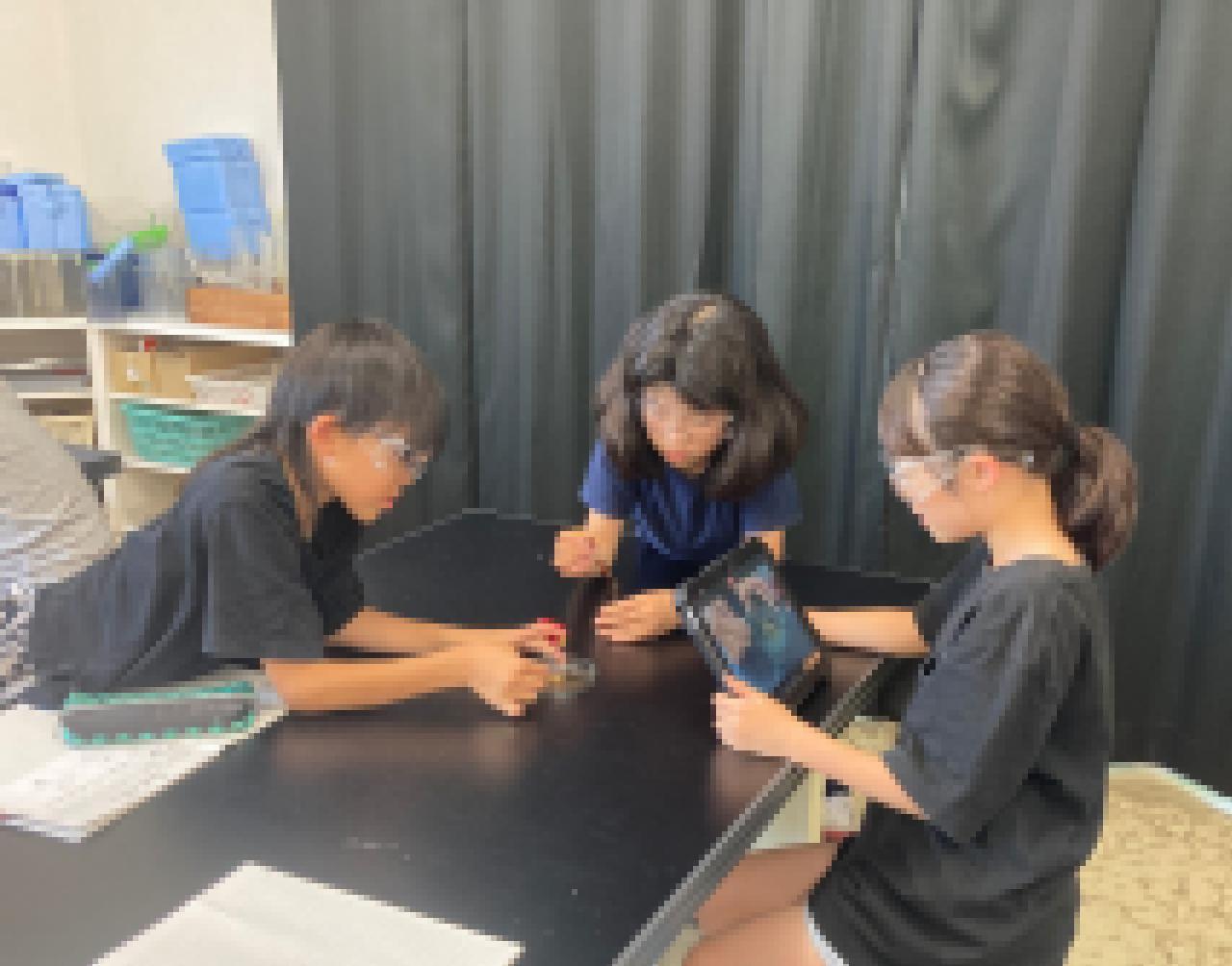
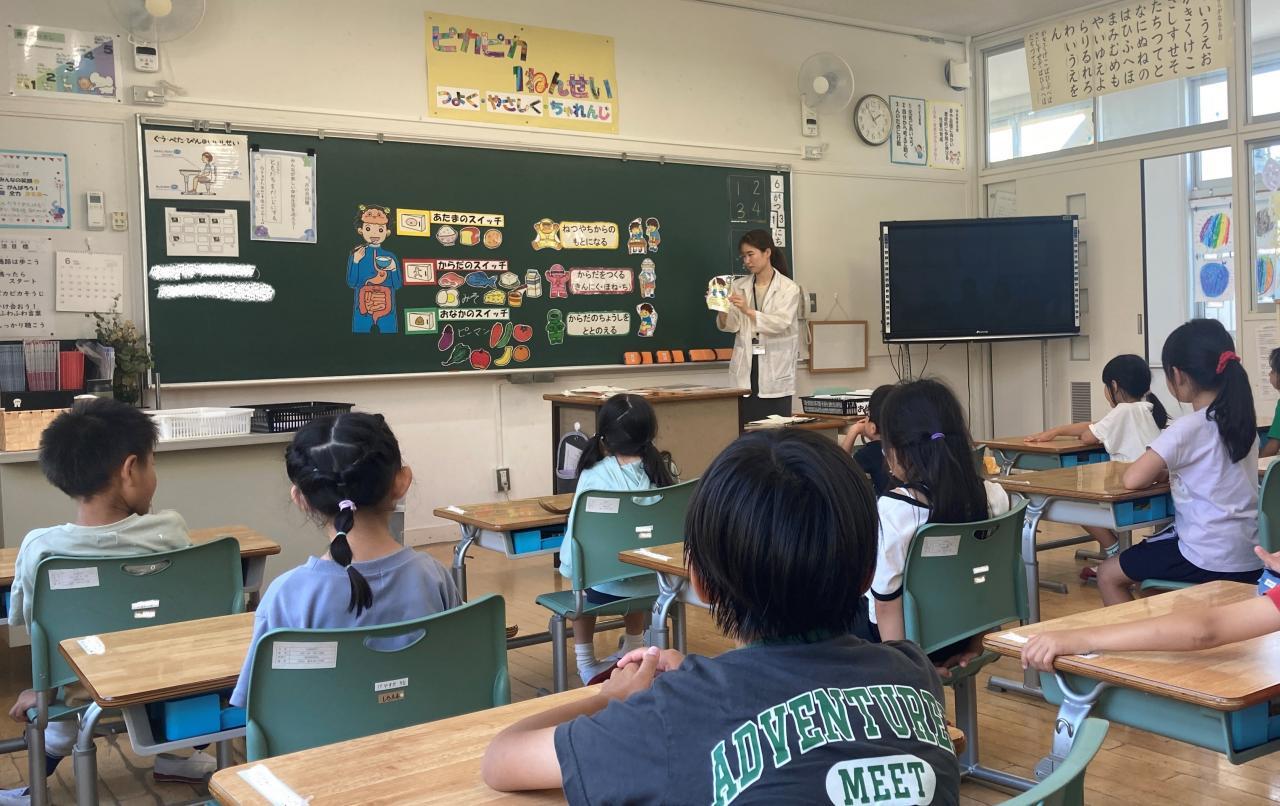


(続きです)
例えば、「Aさんと私」の関係で私に共感的な姿勢がなければ、良い方向へとはすすみません。Aさんとは「友だち」「仕事仲間」「保護者」などいろいろです。
いかに私が正しいことを述べたとしても、相手の気持ちに寄り添えない(共感しない)ならば、双方ともメリットはありません。
共感できることによって、親近感、安心感、正しい理解や、課題があれば解決への促進が生まれます。はじめは意見が違うとしても、お互いの気持ちが通じ合うことを大事にすれば、一方が自分の過ちに気づいたり、双方にとってよい結果が得られたりすることでしょう。
そして、子ども同士であっても「共感的態度」があれば、ケンカ・いじめ等のトラブルは発生しにくくなるそうです。発達段階においては、共感力がまだまだ低かったり、共感的態度を示せなかったりします。子ども同士の関係や集団の中で、安心感や正しい理解を増やしていくためには、共感する力を育てていかなければなりません。
そこで共感力を高める方法として3つあげます。
傾聴すること
自分の意見を言ったり頭の中で考えたりせずに、相手の意見について理解に徹する。
読書習慣をつけること
物語などは、様々な人物の考え方に触れることができる。
他人に関心を持つこと
コミュニティ参加の機会を作り、いろいろな経験から他人視点に置き換えられるようにする。
調べてみると、上記のことが多く書かれていました。子どもたちは日々の生活体験から共感力がついていくのです。が、より高い共感力を身につけるためには、周りの大人たちが共感的な態度で接していくとよいのではないでしょうか。
人生における幸せの最大要因は、良好な人間関係であることが言われています。関係づくりのために共感力の高さは不可欠です。
たとえ、相手の意見が自分とは違うとしても一旦は受け入れる姿勢により、お互いに分かり合おうとする素地がきっとできるはずです。
私も子どもとの対応などに生かしたり、仕事に生かしたりいていこうと思います。今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。