
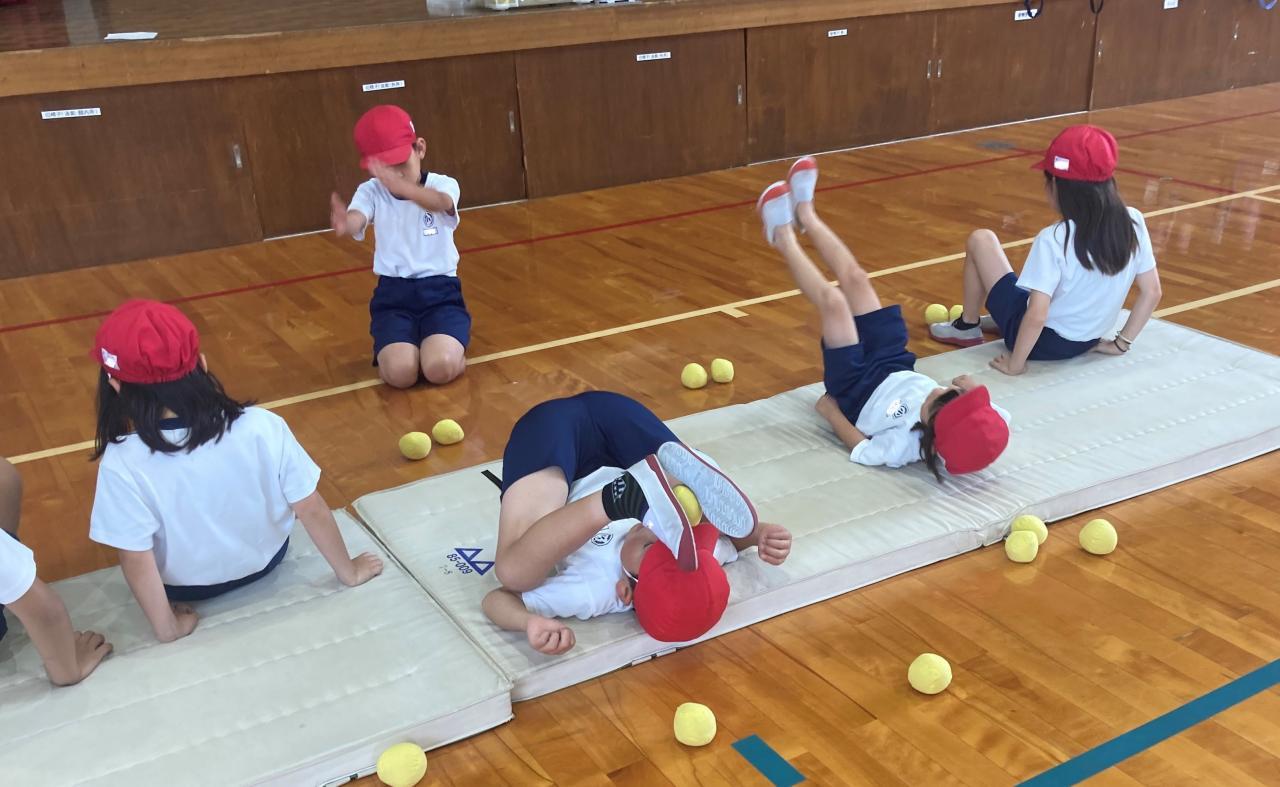
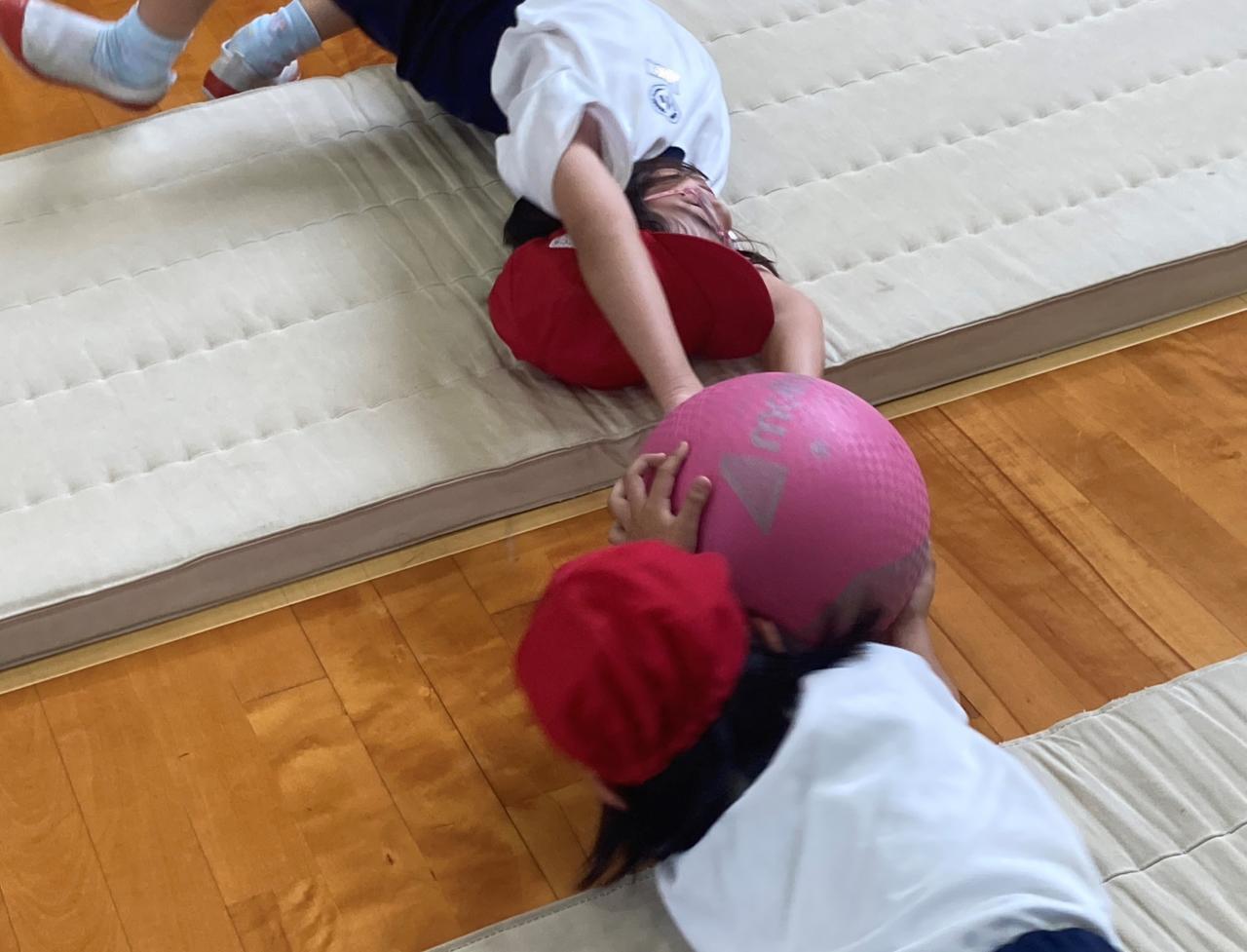


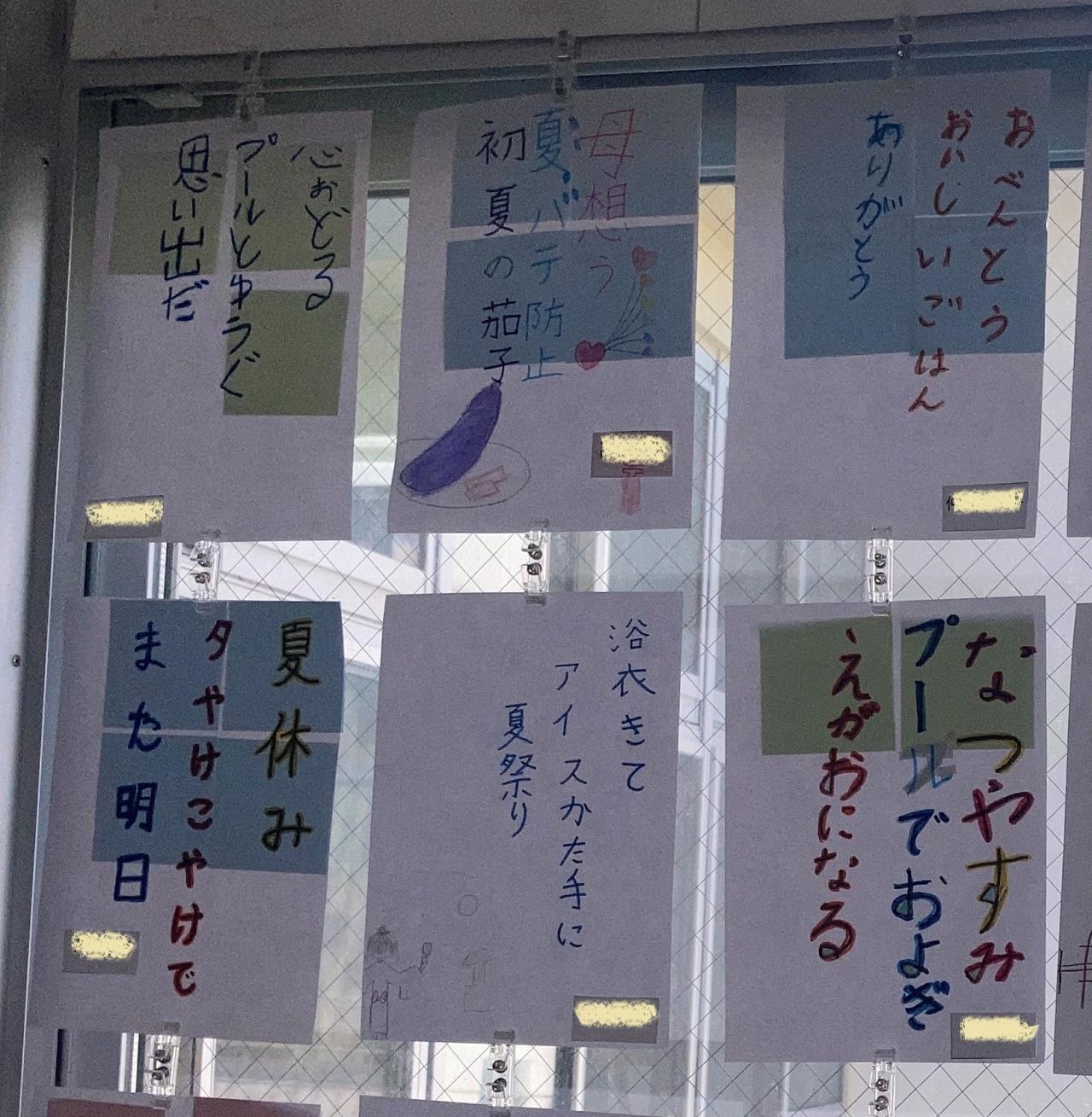






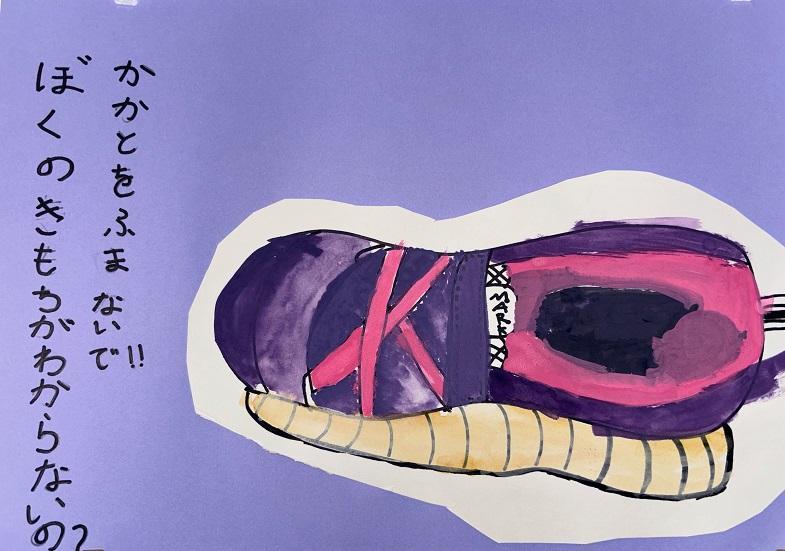
安全対策と聞く力
先日、本校3年生で「川に棲(す)む生き物を見つけよう」をテーマに環境体験学習を実施しました。実際に川に入る(水面がひざの深さまで)わけですが、先だって担任の先生や講師先生から様々な注意があります。
子どもたちにとって、楽しみな学習ですから気持ちが川のほうへ向かいます。するとつい注意を聞く姿勢がおろそかになってしまう児童もいます。
そのたびに、先生は話を聞くように促したり、叱ったりしていました。当然のことです。校外の学習では教室と違い、いろいろな危険を想定します。
当日の川は、流れの少ない日を選んで実施していたといえ、最大限の注意が不可欠です。それを、子どもたちに自覚させなければなりません。
先生の指導が重要であるとともに、子どもたちの聞く力も重要となります。重大な事故につながる場面は、いつ出くわすかわかりません。その時に知識があるのとないのでは、結果に大きな差が出るのではないでしょうか。また、大人がいつも一緒にいるわけではありません。そこで様々な安全教育を行い、場面に応じた対策を伝えています。
その時の理解と以後の記憶のために、話を聞く力や聞こうとする姿勢が大事となります。その時だけ聞こうとしても無理がありますから、普段から子どもたちの聞く力をしっかりと育ててあげなくてはならないと思います。
子どもの聞く力をつけるために、大人がしてはいけないこと
を紹介します。私の過去の経験(教員として親として)でもあります。それは普段から、
「早くして!」「なにしてるの!」などと、叱る言葉を多く使うこと
「でも」「だけど」など、相手の意見を聞き入れない言葉を多く使うこと
です。大人が叱る言葉を日常たくさん使っていると、子どもは嫌な気持ちになり、自分自身を守るために言葉を聞き流すようになってしまいます。
また、「でも」や「だけど」などをよく言われて、自分の意見(言葉や気持ち)を受け入れてくれないと感じると、相手の言葉や気持ちを聞き取ろうとしなくなるはずです。子どもが人の話を聞こうとする気持ちになるためには、叱る言葉や否定につながる言葉を極力少なくしなくてはならないのです。
(続きます)