
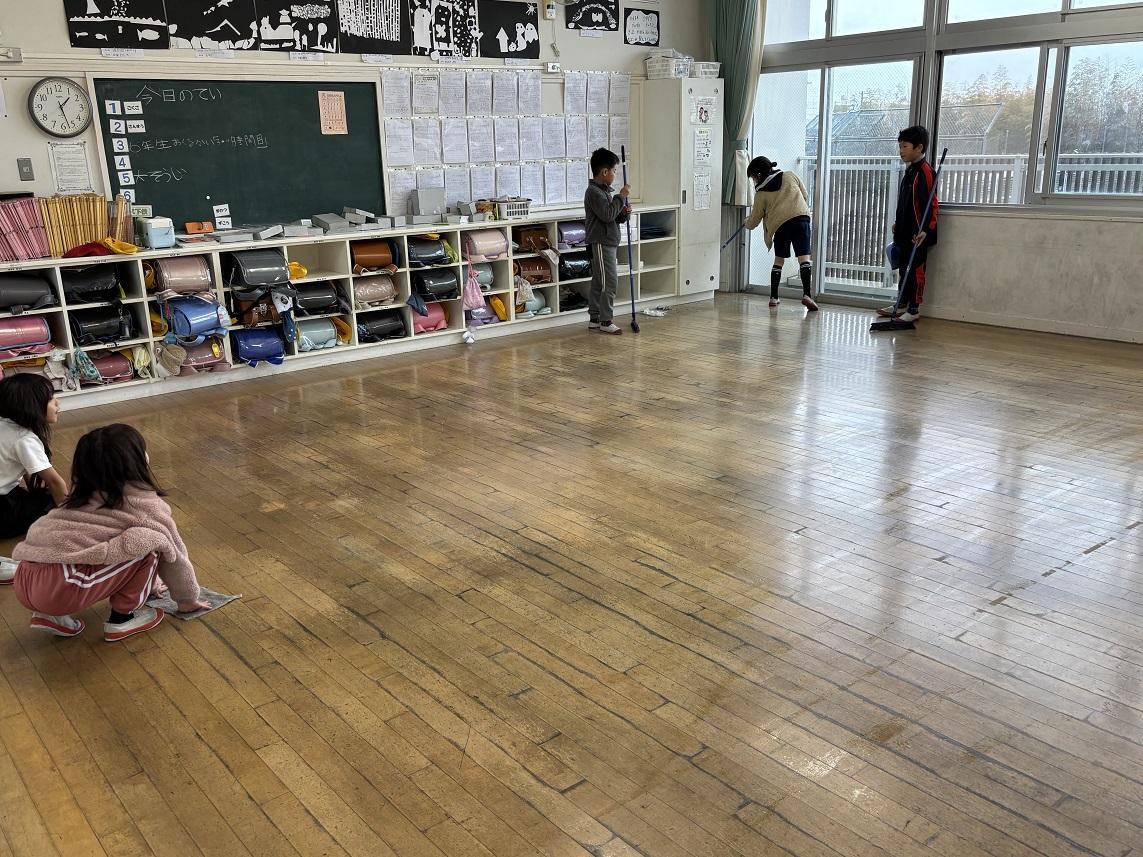

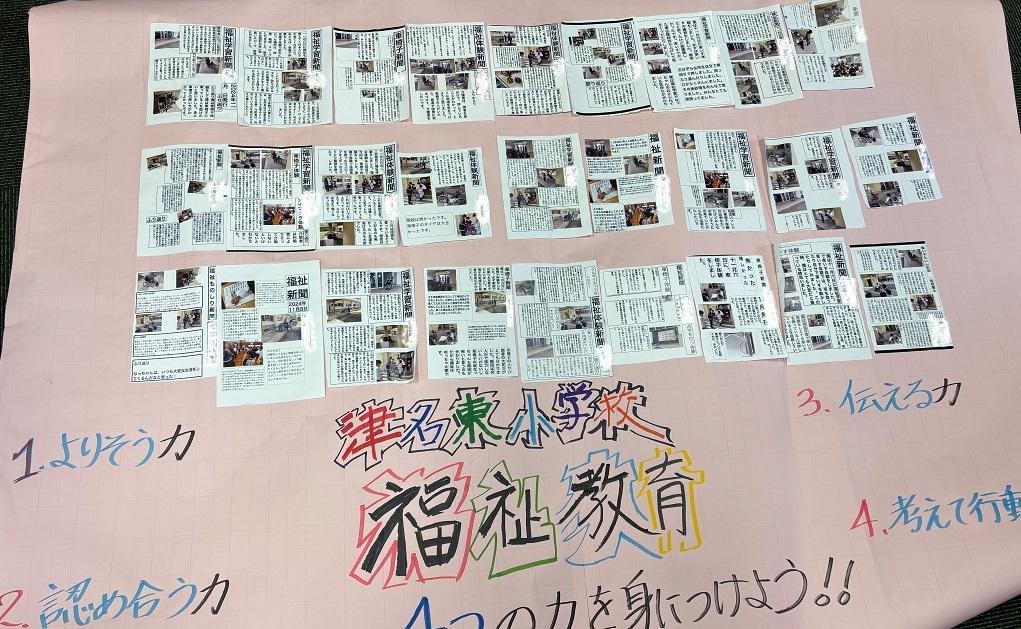

【3月8日】の記事では「ほめ方」について書かせていただきました。今回は「叱り方」について、皆さんと考えてまいります。
叱るのは難しく、私は苦労してきました。おそらく以下のようなしてはいけない叱り方をしていたのだろうと思います。
感情的に叱る
自分の経験上最もダメだったなあと思う叱り方は、「感情的に叱る」ことでした。
言い換えると、自分の腹が立っていただけでした。そこには、相手(子ども)の間違いを理解させ、次の行動を改めさせるような導きはありません。叱られた側も、自分の行動を振り返ろうという気にならなかったばかりか、反抗心も芽生えたことでしょう。
また、大人が感情的に叱る姿を見て育つと、子どもも「嫌なことがあったら怒る」「感情で人を責める」という行動をまねしやすくなるのです。友達やきょうだいとの関係でも、怒りっぽくなったり、手が出たりするようになるのではないでしょうか。
いきなり怒鳴る
次にダメなのは「いきなり怒鳴る」です。
例えば、大きな声で「何やってんの!」「こらー(怒)いいかげんにしろ」です。特に教室内でやってしまうと、当事者以外の子どもたちを驚かせたり、怖がらせたりしてしまいます。
無論、叱られる当事者にとってもマイナス影響となります。いきなり怒鳴られることを繰り返された子どもは、オドオドした性格かまたはピリピリした性格になるそうです。理由は、次の通りです。
いきなり怒鳴られると、子供は自分の行為が叱られる事であると認識していない状態で、突然強いショックを受けることになります。それが繰り返されると、いつ強いショックを受けることになるのか常に心配していなくてはなりません。心が安定せず過ごしているので、内向的な子であればオドオドした性格、外向的な子であればピリピリした性格が形成されます。
そして、いつ怒鳴られるかわからないので、親や教師を避けるようになります。その後も無意識に避けるようになり、心を閉ざしていくでしょう。子どもの様子がおかしい時に「何かあったの?」と優しく聞いたつもりでも「べつに」と返されてしまいます。
大きな声を突然出していいのは、危険回避の時です。例えばボールを追っかけて車道に飛び出そうとしている子どもは止めなくてはなりません。一瞬でも待てないときは大きな声を出します。
また、 いきなり怒鳴らず「やめなければ、大きな声で叱るよ」と言ってあげ、それがいけない行為だということを理解させます。
その他のダメな叱り方
・人格を否定したり他人と比べたりして叱る
例;「お前なんか何をやってもダメだ」「兄ちゃんは、ちゃんとできていたのに」
・過去の失敗を持ち出して叱る
例;「前もしたよね、次もするんだろ」
・長々と説教する
本当に大事なことがぼやけてしまい、伝わらなくなります。
・罰ばかりを与える
子どもは、いけないことの理由や改善策がわかりません。
上記のことは皆さんも気をつけている事柄だと思います。が、叱ることが多くなってしまえば、ついやってしまうかもしれません。(私も)
子どもは自分の行動を深く反省し、次の行動に繋がればいいのです。が、叱られる意味が理解できないと、叱られることを回避するために「うそ、ごまかし、言い訳」を使います。
それが通ってしまえば、正しいことを進める力や相手の気持ちを推しはかる力が育ちません。そうさせないためにも、上記の叱り方を繰り返してしまわないようにしたいものです。
では、どのような叱り方をすればいいのでしょうか。
(続きます)